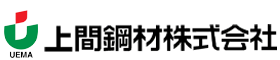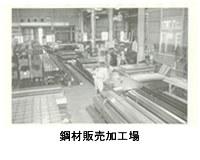発刊を祝う 沖縄県議会議員 安里 進

敬愛する上間義夫氏が自分史を発行されるに当たり、後輩として、この出版をお喜び申し上げますとともに、衷心より敬意を表する次第であります。実は私と義夫氏との関係は、振り返ってみると、義夫氏が名護の城通りに上間金物店を開店したころに始まります。店の開店が一九五七年(昭和三十二年)といいますから、あれこれ四十七年が経過していることになります。
そのころ、私は県立名護高校三年のころで、同期生であった親友の宮城進君(義夫氏の夫人・ヨシさんの弟)と一緒に金物店を訪ねたことがきっかけです。それ以降、義夫氏を身近に感じ、今日でも飲み友達としてお付き合いをさせていただいているところであります。
さて、今般の上間義夫氏の自分史を拝読して、義夫氏が青年時代、ずいぶん苦労され、海人から現在の会社を立ち上げたことに改めて敬意を表するものです。もちろん、それを支えてきた最大の功労者は、奥さんのヨシさんであったことは言うまでもありません。「夫唱婦随」で幾多の苦難を乗り越えての会社設立であったろう、と推察申し上げるものであります。
自分史の文中、今は絶えましたが、名護のヒートゥ狩りの話、名護の食文化の話など、興味深く読ませていただきました。また「我部祖河の偉人」の章では、我部祖河出身の上間幸助氏が沖縄自由民権運動で名をはせた謝花昇や移民の父、当山久三らと運動を共にしたという歴史的事実は、沖縄県民として忘れてはならぬものだと改めて認識させられました。
上間鋼材株式会社、ウエマ産業株式会社も今は息子の雅之氏に引き継がれ、会社体制は磐石なものになっているようであります。雅之さんは現在、沖縄県商工会青年部連合会の会長に就任されており、社会的にも活躍し、実に頼もしい限りであります。
終わりに、十分意を尽くしていませんが、義夫氏が私達後輩のために、ご自愛され、余生を悠々自適に過ごされることを祈念申し上げ、自分史出版の祝辞とさせていただきます。
まえがき 上間 義夫
一九五七年(昭和三十二年)に私とヨシで立ち上げた個人経営の店(上間金物店)ができてから早くも半世紀。ずいぶん前のことだが、創業時の辛さ、厳しさは昨日の出来事のように私の脳裏に焼き付いている。
台湾での漁業生活、ラバウルでの戦争体験などが遠い記憶のかなたにあるが、運が味方してくれたのか、海上で、あるいは戦場で命を落とすこともなく、無事、沖縄に生還を果たし、ヨシと巡り合った。運命的な出会いとしか思えないが、五十五年の長き年月、共に連れ添い、ここまでたどり着いた。
上間金物店も上間鋼材株式会社、ウエマ産業株式会社として大きく発展し、長男の雅之に引き継ぐことができた。実に感無量である。願わくば、これらの会社が新しい時代の風を受け、波に乗って、激動の二十一世紀をたくましく乗り越えてほしいものだ。そして事業の継続、発展を成し遂げてほしいと祈るばかりである。
私は一男五女の子宝に恵まれた。私は仕事一筋に生きた面が強く、子供たちが満足できるような接し方をしてきたとは決して思えないが、父親としては家族に経済的な負担をかけぬよう、私なりに懸命に努力してきたことは事実である。一人ひとりの子供たちが私をどう思っているのか知らないが、子供たちも私の気持ちを汲んでこれからも頑張ってほしいと切に願っている。
やそじ(八十路)を迎える年齢に達した。私の古里、我部祖河への思いも日に日に強くなっている。我部祖河の発展に関しては、今後とも協力し、支援していくつもりである。これまでの生き方を「誠ーわが半生の記」としてまとめる機会を得た。大それたことを述べるつもりは毛頭ないが、一庶民の生き方として読んでいただければ、これに過ぎる喜びはない。
二〇〇四年夏
生い立ち

沖縄本島の北部を俗に山原という。自然が色濃く残る山々に囲まれ、薪や材木を本島中南部に供出してきた長い歴史がある。一九二四年(大正十三年)六月二十五日、私は雄大な自然に育まれた旧羽地村の我部祖河で、農業を営む父源清、母カマダの三男として生まれた。
羽地村という自治体の名は今はない。現在は名護市となっているが、この名護市は沖縄が本土復帰する二年前の一九七〇年(昭和四十五年)八月一日に名護町、羽地村、屋部村、屋我地村、久志村の五町村が合併して誕生したものである。
旧羽地村は沖縄本島と本部半島が交錯する湾曲する湾曲部にある。屋我地島と奥武島が浮かぶ羽地内海を抱く風光明媚な農村地帯であった。日本の観光名所の一つ、江ノ島(神奈川県在)にも匹敵するといわれるその美しさは、琉球民謡にも歌われるほどだ。
私が生まれた我部祖河は名護市の中心街から北西部に約四・五キロ離れた所にある。集落の北東部には我部祖河川が流れ、一帯は羽地田袋と呼ばれ、昔から米づくりが盛んなところとして知られていた。
我部祖河の村を興したのはナカヌヤー(仲ノ屋)の先祖の上間大主だったという言い伝えがある。伝説によると、上間大主は本部半島の北東にある古宇利島のウフェーク家に生まれた。そこから伊平屋島に渡り、暮らしていたが、しばらくして国頭間切の宜名真に渡った。しかし、すぐまた源河村に移り住んだ。上間大主はそこに落ち着くこともなく、真喜屋村に移り、暮らした。そんな時だった。ある日、村の多野岳に登り、周辺を見渡したところ、今の我部祖河辺りに大変いい土地が見つかった。そこで上間大主はそこを安住の地と決めて移り住むことになった。それが我部祖河の始まりだという。そのような経緯もあり、集落には上間性を名乗る人たちが多い。
名護市の統計によると、我部祖河の人口は明治十三年には一○一戸で五百三十七人いた。昭和十四年には一二七戸、五百五人となっていることから私の子供時代も集落の人口は百戸前後で五百人ぐらいだったと思う。
私が通った羽地尋常高等小学校は隣の集落の振慶名にあった。家から約二キロぐらい離れた所にあり、歩いて二、三十分かかった。私の小学校時代は、どこの家庭でも自給自足の生活が普通だった。ただ水田が多かったので、米がたくさん採れた時には名護の町へ米を売りに出掛け、金に換えていたことを覚えている。要するに米は換金作物だったのである。このため日常の主食はサツマイモだった。朝、昼、晩芋を食べた。米はたまに食べる程度だったのである。家が農家だったので、学校から帰った後は、草刈りをするのが日課となっていた。集落では子供が鎌を持ち、近くの山で草刈りをして家業(農業)を手伝うのは、ごく自然のことで、どこの家庭でも見られる姿だった。
小学校へは裸足で歩いていった。履く靴がなかった。あのころは私だけでなく、ほとんどの子供たちは裸足で通学した。集落の友達五、六人と連れ立って、おしゃべりしながら通ったものである。現在見られるような路線バスというものがなく、行き帰り裸足。難儀で不便だったが、友達と楽しく語り合いながら通ったことは、今振り返ってみると、懐かしい良き思い出としてよみがえってくる。私の記憶では同じ集落の同級生は男が四人、女が三人、計七人だったように思う。
朝は大体七時ごろに起床した。朝ご飯を食べ、登校の準備をして家を出るのは午前八時ごろ。それから二十.三十分かけて学校へ行く。授業時間は一日五時間ぐらいだった。授業科目は国語、算数、理科、社会(歴史)、体操などだった。また特異な科目として農業の時間もあった。野菜や芋など作っていた。家の草刈り作業は学校から帰って来てからやった。勉強はあまり好きではなく、よく遊び回ったものである。私のあだ名は、頭の毛が時計の針と反対方向にグルグル回っていたので、「ムコーマキー」と呼ばれていた。学科の勉強より体育、その体育より遊びが好きだった。
私達は集落内にあったムイグヮー(小高い丘)に登り、高跳び、幅跳びなどして遊んだ。もちろん、遊び道具は家から角材や釘など持ち出し、自分達で作った。高跳びのつい立ては高さが一八〇センチぐらいはあった。当時はいろいろなオモチャも自分達で作り、それを使って遊んだものである。本当に勉強は二番だった。純粋無垢な学童期だったように思う。母親の栄養管理も行き届いていたのか、小学校時代は、これといった病気にかかったこともない。病気とはいえないが、たまに風邪をひく程度だった。「遊び好き人間」という意味では私は「ウーマクー」(したたか者)だったかもしれない。
学校の先生と言えば、まだ記憶に残っているのは女教師の屋部先生だ。同じ教員の金城清徳先生と結婚し、金城性を名乗っていたが、我々子供達は結婚後も「屋部先生」と呼んでいた。清徳先生には小学六年と高等一年の時にお世話になった。また高等一年の時には平敷先生にも教えてもらった。
私達子供は学校から帰って草刈りするのが日課となっていた。牛や馬の飼料である草刈りをした後、ムイグヮーへ行って遊んだものだ。
当時、農家では牛と馬は農耕用に飼っていたが、私の家では子牛を仕入れ、これを四、五ヶ月ぐらい育てて売りに出していた。この畜産も我が家の一つの収入源となっていたようだ。畑ではサツマイモ、ジャガイモ、お茶など栽培していた。田んぼではもちろん、米を作っていたが、家族で食べる程度のものだった。
米が多く採れた時には名護の町へ売りに行っていた。
しかし、米は毎日は食べられなかった。主食は芋だったので、米のご飯が食べられる時は子供ながらに嬉しかった。そういう意味では米は貴重な食べ物だったのである。普段は蒸し芋とか軟らかいカンダバー・ジューシー(芋のかずらの雑炊)しか食べられなかった。だから、「おいしい食べ物は何ですか?」と、問われると、「ご飯です」と答えたものである。おいしいものが食べられる日は、お盆とか正月の時ぐらいだった。米のご飯も出るし、肉もある。今の人たちは何一つ不自由なく、いつでも米が食べられる。逆に物が豊か過ぎて残ったご飯も捨てたりする。戦前の厳しい食生活を体験した者からすると、実にもったいない話だ。
食べ盛りの子供たちにとって家の食事だけでは満足できない。このために近くの山で木の実を採ってよく食べたものである。ギーマとかイチゴとかヤマモモとか、いろいろな果実を採った。ヤマモモは一般家庭の庭先にも植えられていたが、我部祖河では植栽している農家は少なかった。四、五軒はあっただろうか。沖縄のヤマモモは本土のモモより小粒だが、とてもおいしかった。ヤマモモは庶民生活とも密着していた。民謡で「桃売いアングヮー(おばさん)」と歌われたほどである。
浜下り(旧三月三日)の時期には潮干狩りに出掛けた。お汁に入れて食べるアサリを、島の人達は「ミナー」と呼んでいたが、そのミナーをよく採った。
私達の小学校時代は方言札があった。国の方針で沖縄県民は方言は使わないで標準語を使うよう指導が徹底されていた。学校で方言を使っているところを見つけられると、方言札を首から吊るされたものだ。この方言札は昭和初期に徹底指導されたという。
集落内に武田薬草園がありコカが栽培されていた。人手不足だったのだろう、時々、肥やしの運搬作業などの仕事があった。日当は大人五〇銭、子供たちは二十五銭だったが、結構いい小遣い稼ぎとなった。このコカを夜通し乾燥させる仕事に就いた場合には賃金が一〇銭アップしたのを覚えている。刈り取られたコカは手でもんだあと、乾燥させ、箱に詰めて本土へ出荷されていた。
村を揺さぶった嵐山事件
のどかな羽地村にふって湧いたような事件が起きた。隣接の町村を巻き込んだらい療養所建設に反対する事件である。沖縄県当局は旧羽地村の高台にある嵐山にらい療養所の施設を建設する予定だったが、これに反対する地域住民の強い反対運動に遭遇し、断念した事件である。この反対運動で百人余が検挙され、うち十五人が起訴されたが、この事件は建設予定場所の地名を取って「嵐山事件」と呼ばれている。
らい病はらい菌の感染による慢性伝染病で、戦前は不治の病として人々から恐れられていた。患者は世界的にインドに最も多く、続いてアフリカ、東南アジア、中国、中南米などとなっているが、日本には約一万人はいるとされている。現在、病名はらい菌を発見したノルウェーの医学者の名にちなんでハンセン病と呼ばれるようになった。今日、日本での発生例はほとんどなく、根治できる病気である。
事件は私が八歳で、小学生の頃に起きた。一九三一年(昭和六年)三月、村の青年が嵐山へ薪を採りに行く途中、雑木林が切り取られ、大きな広場ができているのに気付いた。見ると。らい病患者療養所の建設現場だった。おどろいた二人は早速、字(集落)の区長に通報したのが事件のきっかけである。(一九九九年十二月発行「我部祖河誌」から)。 風光明媚な嵐山は、村内の我部祖河、呉我、古我知の三集落の水源地に当たるとともに、隣村の今帰仁村、屋部村の河川にも大きな影響を与えていたことから、これらの村にもたちまちのうちにうわさが飛び火し、療養所建設反対運動が起きた。
村民の騒動は私たち小学生まで影響した。字の青年たちは各家庭を回り、子供たちを学校に行かせぬよう全員休校とするよう指示した。同時に河知産業組合(現在の農協)前に集合するよう村民に呼び掛けた。集合場所には我部祖河、古我知、呉我の住民がムシロ旗を掲げ、建設反対の気勢を上げていた。一行は「ワッショイ、ワッショイ」と声を掛け合い、伊佐川三叉路、田井等、川上を通り、羽地尋常高等小学校の校庭を一周したあと、村の中尾次、真喜屋を通り、稲嶺小学校の校庭を一周、再び村内をデモ行進し、呉我の橋のたもとに終結した。会場では療養所施設の建設に断固反対することを確認し合い、子供たちにはしばらく休校することを命じ、全員でガンバロウ三唱して解散した。
反対運動は村を巻き込んだ。療養所の建設に反対する村長、村職員、村議員は総辞職を決行するとともに、税金の不納運動にまで広がった。このため県当局は吏員を四、五人を派遣し、役場で職務を代行したが、村政は混乱した。児童生徒の休校措置もあり、村全体が「異常事態」に陥った。このような中、名護警察署は反対運動の人たち百人余を検挙した。検挙された人たちは数日間、取り調べを受けたあと、釈放された。だが、主要メンバーと目された十五人の幹部は身柄を那覇警察署に移され、七十日余り、拘置されたあと、裁判所に起訴された。十五人は留置所で拘留され、検事の厳しい取り調べを受けた。この間、村民の有志は交代で那覇警察署へ出向き、飲み物や食べ物を差し入れするなど、全面的に支援した。
療養所建設反対運動は翌年の一九三二年(昭和七年)まで続いた。県当局はついに嵐山での建設を断念、離島の屋我地島に変更し、建設することになった。我部祖河の人たちは、長い拘留生活に耐えた十五人の人たち(故人)に対し、今でも敬意の念を抱いている。 十五人の中には戦前戦後、沖縄のジャーナリストとして活躍した上地一史氏がいる。上地氏は一九○三年(明治三十六年)十一月、旧屋我地村(現名護市)で生まれた。当時、二十八歳と正義感にあふれた、多感な青年だった。反骨精神が強く、一九三九年(昭和十四年)には沖縄朝日新聞記者として健筆を振るった。
戦後は羽地村助役、沖縄水産組合連合会副会長など務めたが、記者魂はさめやらず、四八年(昭和二十三年)、先輩の高嶺朝光、座安盛徳、豊平良顕の各氏らと共に沖縄タイムス社を創刊し、その取締役編集局長に就任した。六十五年(昭和四十年)にはタイムス社の代表取締役社長になり、経営者として敏腕を振るったが、七四年(昭和四十九年)九月、ヨーロッパ産業視察中にTWA航空機墜落事故に遭遇、死亡した。享年七十歳だった。 戦前、不治の病として恐れられていたハンセン病は、その後、治療薬が開発され、現在では完全に治癒する病気となっている。一九九六年(平成八年)には「らい予防法」も廃止され、回復者の社会復帰が進んでいる。しかし、まだ社会の一部に差別と偏見が残っているが、私たちはこの偏見と差別をなくしていきたいものだ。
(平成十一年十二月発行「我部祖河誌」参照)
台湾行きを決意

振慶名にあった羽地尋常高等小学校は高等一年までしかなかった。高等二年に進級するにはさらに隣の仲尾次へ通う必要があった。私は家庭的な理由から進級することを断念し、同小学校を卒業した。その時、十五歳になっていた。今の新制中学校卒業とほぼ同じ年齢に当たる。学校を出て、家でぶらぶらするわけにもいかないので、しばらくは武田薬草園で働いた。
その後、我部祖河の寄合原から切り取った琉球松の木材を場車道まで運ぶ仕事をした。寄合原から馬車道まで運ぶ仕事をした。寄合原から馬車道までの道のりは一キロはあっただろうか。木材は肩に担いで運ぶが、これは重労働である。大きさや重さによって賃金は決まっていた。かなり重たい木材を運ぶ人夫もいたが、私の場合、直径は約五寸(一五センチ)、長さ約六尺(一八○センチ)、重さ約四十斤(二四キロ)の木材を運搬した。一日で十往復はしたように思う。この琉球松を使って名護の製材所では、家具や砂糖樽など作っていた。
この仕事も長くは続かず、今度は名護町にある山口自転車店で丁稚奉公に出た。もちろんのこと、山口さんの家に寝泊まりしての仕事である。仕事の内容は朝六時ごろ、起床し、自転車を二、三台きれいに磨いてから朝食を取る。日中はパンク修理などだった。
そのころ、自転車は高価な乗り物だった。我部祖河内でも一、二台はあるかといったぐらい数少なかったのである。このため自転車を販売し、修理する店も少なく、山口自転車店では買ったお客さんの自転車を預かり、掃除し、管理することもしていたので、結構、もうけていたと思う。
この自転車店は名護町内の羽地通りにあった。賃金は日当にして二十銭はあった。大人の一般労働者で日当五十銭の時代だから、少年がもらう給与としては、いい方だった。いただいた給料は実家にも多少入れたが、大半は自分で使った。
住み込み仕事の嫌なことは、山口さん一家と一緒に食事を取ることだった。山口さんは本土出身の方だったので、食事の際、温かいご飯を入れたおひつを出す。ご飯は自分でおひつから取り出して碗に入れるので、お代わりするのが辛い。皆の視線があるので、自由にお代わりができない。こちらは育ち盛り、食べ盛りなので、本当なら何杯もお代わりしたいが、家族の手前、そうもいかない。結局、満腹しないままに食事時間が終わるので、いつも空腹感があった。このため、その生活に耐えられなくなって自転車店を辞めた。
そんな時だった。我部祖河出身で隣の台湾で漁業関係の仕事をしている伊豆味源徳さんが若者を募集していることが分かった。四年勤務を条件に一人当たり三百円の報酬を出すという。友達の誘いに私の心は揺れた。その時、もう十七歳になっていたが、実は家庭的な問題で私は親への不信感を日々、募らせ、反抗的になっていた。台湾行きを親に話すと、必ず反対されることは明らかだった。それで私は内緒で台湾行きを決意、友達三人で出稼ぎに行くことにした。
台湾行きの案内役は伊豆味さんの奥さんだった。四人一緒に那覇行きのバスに乗り込んだ。船は那覇港から出るが、出発の日まで、あと三日はある。三人とも那覇市内の民宿で寝泊りしたが、そこで食べた料理が実にうまかった。豆腐とモヤシを混ぜて油で炒めた「マーミナーチャンプルー」だった。今でこそ、マーミナーチャンプルーは日常的に食べられる庶民の味だが、その当時はヤンバルでは食べたことがない代物だったのである。物珍しさもあって、三人とも「おいしい、おいしい」と連発して食べたことを覚えている。
また那覇滞在中、奥さんの親戚が料亭をしていたので、その関係もあって料亭に連れて行ってもらったことがある。食事を取りながら、ジュリ馬の踊りを見せてもらった。当時はジュリ(那覇市辻町の遊女)の意味さえ分からず、料理と踊りを楽しんだものだ。ジュリ馬は今では、那覇市の観光名物となっているが、これは旧暦一月二十日の二十日正月に那覇の辻町で行わる恒例の祭祀となっている。馬の頭部を形取った飾り物をジュリが胴体に固定し、掛け声をして街中を練り歩くもので、商売繁盛と豊作を祈願をする。
船は確か沖島丸だったと思う。三○○○トンはあっただろうか。初めての船旅である。船を見たときにはその大きさにびっくりした。夢を見ているような感じだった。沖島丸は多くの人たちに見送られ、那覇港を離れた。船は白波を立てながら台湾の北に位置する港町、基隆を一路目指し、航海する。
船は見かけとは違い、設備は貧弱だった。我々は三等室に泊まったが、冷房もなく暑かった。三等室は船底である。エンジン音と油のにおいで気分が悪くなった。このため、ちょくちょく甲板に出ては長い時間を過ごしたが、目的地の基隆まで一昼夜半はかかった。無事、基隆に着いた。我々四人はすぐに台湾の南側にある高雄へ行くために汽車に乗った。高雄は南の大都市・台南よりさらに南下した所に位置する商業都市である。良港を抱え、東南アジアへの玄関港として知られる。我々が乗った汽車は鈍行だった。汽車で二泊してやっと高雄に到着した。
高雄を拠点にした漁生活が始まったが、漁船の整備などもあって約一ヶ月は休養した。我部祖河から来た我々三人の仕事は、漁船に乗り、先輩乗組員らと一緒にタカセ貝、ヒロセ貝を採り、港に持ち帰ってくることである。漁船は五○トンあった。この船には船長、コック、機関長のほか、漁夫ら二十四、五人が乗り込んだ。出漁すると、半年は帰って来ない。
我々の仕事は魚漁とは違う。洋服のボタンの材料となるタカセ貝、ヒロセ貝の採取である。これらの貝は高く売れたようで、商品は全部本土へ出荷された。我々は出漁に出た。漁場は広かった。フィリッピンと台湾の境界となっているバシー海峡を越えた海域である。高雄を出発して目的地に着くまで半月はかかった。小さな島々の環礁(リーフ)内で潜り、貝類を採取した。私の記憶ではベトナム沖にある中国領・海南島の近くまで漁をした。この間、台風にも遭遇した。船いっぱい貝を積んで我々は半年ぶりに寄港した。乗組員は大きな任務を果たし、喜び勇んで高雄の土を踏んだ。
皆の表情には無事、台湾に帰ってきたという喜びと安堵感が漂っていた。漁を通して私は貝採りの技術を学んだほか、我部祖河ではまるきり駄目だった水泳も身に付けることができた。私にとっては、お金の報酬とは別の成果だったといっていい。
ラバウルで終戦迎える

しばらく高雄で休養してまた漁に出ることになった。今度は台湾の領海内である澎湖水道を越えた所にある澎湖島での漁生活が待っていた。高雄から遅い船足で八十時間はかかる漁港の町である。澎湖島を基地に漁に出たが、今度は貝採りと違って本来の魚漁だった。マグロ船にも乗り、底引き網漁業を主体とする手繰り船にも乗った。私は完全にウミンチュの一員になっていた。
私が澎湖島にいる時に太平洋戦争が始まった。台湾では戦争の影響はそれほど大きくなかったが、我々は軍属として日本軍に徴用され、糧秣の調達、運搬の任務を負わされたのである。一九四三年(昭和十八年)、我々は澎湖島を出て高雄、フィリッピンのマニラをへてパプアニューギニアのラバウルに着いた。軍に徴用された漁船はかなりの数に上っていた。私の記憶では三十隻はあったと思う。我々の船団には海軍の護衛艦が付き、航海の安全を期すという物々しさであった。途中に立ち寄ったマニラには一週間滞在した。ラバウルでは漁業に従事し、追い込み漁で魚捕りをした。
我々が所属した部隊の責任者は、那覇市出身の山口大隊長だった。我々は五、六人で漁労班を結成し、グループで漁に励んだ。山口大隊長は我々に好意的で、配給品の乾パンや煙草などを多めにくれた。
戦時でも米軍の攻撃がない場合は漁業には何ら差し支えがなかった。しかし、戦況が悪化し、米軍の空襲が激しくなると、漁に出られない。船は敵機に見つかり、攻撃の目標とされるからだ。仕方なく我々は空襲の合間を縫って、港から一、二キロ離れた海岸に行き、ダイナマイトを仕掛けて漁をしたものだ。一帯は豊かな漁場で魚がよく捕れた。これで我々は腹を満たすことができた。
ラバウルは戦争さえなかったならば、住む所としては最高だった。島の近くに豊かな漁場があるうえ、土地は肥えていた。野生のパパイアやバナナなど熱帯果樹も島のあちこちに自然に生えており、食べるのに不自由しなかったからだ。島の人たちは人なつこく、親切だった。平和な世の中なら、住んでもいいと思ったぐらいである。機会があれば、再び訪れてみたい島の一つである。
ラバウル生活は二年を超えた。一九四五年(昭和二十年)八月十五日、日本はポツダム宣言を受諾し、無条件降伏した。日本軍が仕掛けたハワイの真珠湾攻撃から三年と八ヶ月。軍部の独走の結果、多くの国民が戦争の犠牲になった。一方、私の故郷・沖縄では激しい地上戦が繰り広げられ、日米合わせて二十万余の人々の命が奪われた。 ラバウルで終戦を迎えたが、すぐに日本へ帰ることはできなかった。日本への帰還が許されたのは翌年の四六年(昭和二十一年)冬。我々は米軍の船に乗せられた。船内は元日本兵や軍属など復員者でいっぱいだった。食事の時には乾パンやにぎりなどが配給され、問題はなかったが、船内はごった返し寝るスペースがないのには閉口した。横になって寝ることができなかったのである。このため、ほとんどの人が座って寝るといった状態だった。これが大変きつかった。
長い航路の末、愛知県の名古屋港に入港した。港でシラミ取りの殺虫剤・DDTを頭からたっぷりかけられた。DDTはメリケン粉状の白い粉末だったが、においはきつかった。名古屋で二日間、収容されたあと、大洋漁業株式会社の本社がある山口県の下関へ行った。下関では三カ月間、手繰り船に乗り、日本海で漁をした。日本海は豊かな漁場で、タイやイカ、エソ、たまにフカなどがたくさん獲れた。魚を満載して下関港に帰り、また漁場に向かう。私は下関滞在中、三航海した。
大洋漁業の今昔
ここで大変お世話になった大洋漁業株式会社について触れてみたい。台湾の澎湖島での底引き網漁、ラバウルでの漁師生活で私たち漁民の手足となって活躍してくれたのは、実に大洋漁業の手繰り船だったのである。
大洋漁業の歴史は実に古い。一八八〇年(明治十三年)、中部幾次郎が興した会社である。家業である鮮魚の仲買、運搬業から立ち上げた。明治末期、事業の本拠を兵庫県明石から山口県下関に移した。大正時代には土佐捕鯨を買収し、捕鯨事業に着手した。太平洋戦争さなかの一九四三年(昭和十八年)、西大洋漁業統制株式会社に社名を変更。戦争では多くの漁船が日本軍に徴用され、漁船の大半を失うという痛手をこうむった。
戦後、大洋漁業株式会社として再出発。四九年(同二十四年)にはは大洋球団(現横浜ベイスターズ)を設立するまで会社は大きく成長した。一九五二年(同二十七年)には魚肉ハム・ソーセージを発売した。翌年には「マルは」(丸の円形に「は」の文字)のブランドでマルハ・ソーセージを本格的な生産に入った。
九三年(平成五年)に新しい商標を導入するとともに、マルハ株式会社と社名を変更し、今日に至っている。
私にはマルハ㈱の社名よりも大洋漁業のイメージが強い。しかし、大洋漁業の精神はマルハに確実に受け継がれている。水産業では長年培ってきたマグロ延縄、トロール、まき網などの漁法により世界のさまざまな海で漁獲活動を繰り広げている。マルハグループの水産産業は、グループの売上の七四%、営業利益の六二%を占め、社の収益事業の柱となっている。さらに日本人に人気の高いクロマグロの養殖事業を奄美大島で展開し、日本のトップブランドの確立に向けて健闘中である。稚魚を二年半で六○キロまでに育て上げるクロマグロを二〇〇五年度には一五、〇〇〇本まで増産する勢いだ。ちなみに二〇〇二年三月期の売上高は二千九百三十億円、経常利益は十八億七千万円だった。
二〇〇三年(平成十五年)七月、私は五十七年ぶりに山口下関市を家内のヨシと一緒に訪れた。大洋漁業の看板は既になく、マルハ下関支社を訪れたが、懐かしい海の香りに昔を偲んだ。支社長室で大洋漁業の歴代社長の銅像を見学したり、魚のセリ市場を見て回ったり、社員食堂で食事を取ったりして楽しいひと時を過ごした。また漁港では、手繰り船を見ては、若かりしころの自分を思い出し感慨にふけたものである。旅の記念に手繰り船をカメラに収め、持ち帰ってきた。
廃墟の中から
下関で漁業に従事したあと、再び名古屋に戻り、沖縄へ帰還する復員者と一緒に、米軍の船で故郷へ帰ることになった。戦後初めて見る那覇の街は、焼け野原と化し、まだ戦争の爪跡が色濃く残っていた。港には家族の姿はなかった。我々は米軍のトラックに乗せられ、急ぎ羽地へと向かった。
我部祖河も戦争の爪跡が残っていた。集落に着いたが、人々はテント小屋暮らしを余儀なくされていた。木造住宅の家々は空襲で焼かれたので、村人は粗末なテントを張り、その日暮らしの生活をしていたのである。私は義理の兄弟、岸本徳勇さんの家に仮住まいしながら、今後のことを考えていた。
「畑仕事では食っていけないし、農業をしていく自信もない。私には集落の人たちとは違う漁の経験がある。海外での漁業経験を生かし、海の仕事をやろう。村を一歩飛び出せば、そこは海だ。漁業で生計を立てていく以外にない」とー。
幸い、集落内にラバウル時代の戦友がいたので、その人と一緒に今帰仁村の古宇利島に渡り、そこに移り住み、魚釣りをしながら、しばらく生活していた。
そのような生活を送っているうちに、私の結婚話が持ち上がった。同郷の宮城ヨシさんとの婚約である。ヨシさんは同じ我部祖河に住んでいた宮城幸蔵さん、マツさんの二女で、一九二七年(昭和二年)九月十日生まれだった。私とは三歳年下である。親戚や親の勧めもあって、結婚話はすんなりまとまった。宮城さん一家はヨシさんも含め、子供五人(三男二女)の七人家族だった。
戦後のドサクサ時代である。食べていくにも不自由な時世だった。生活物資も極端に少なく、人々は物々交換しながら生きていた。戦後、ヨシさん家族は嵐山近くに避難小屋を建てて生活していた。幸蔵さんは農業していたが、それだけでは食っていけなかった。ヨシさんは家計を助けるために、刈り取った稲で藁をなう仕事もした。もちろん、家に藁をなう機械があったわけではない。製縄機を持っている農家に雇われ、縄作りをしたのである。
縄作りは根気の要る仕事だった。縄は一日で五巻ぐらい作ったという。わずかな賃金だったが、その当時は仕事らしい仕事もない時代だったので、我慢するしかなかった。
ヨシさんと所帯を持ったのは四八年(昭和二十三年)春。私が二十四歳で、ヨシさんが二十一歳だった。翌年(昭和二十四年)四月二十三日には長女の淳子が生まれた。 結婚した当初は我部祖河の妻の実家に居候していたが、本格的に漁業に従事することになって名護の町に引っ越した。そのきっかけをつくってくれたのは名護の町に住んでいた義理の姉である。夫は漁師をしていたので、「あんたもウミンチュになりなさい」と勧められたのである。結婚したてのころは生活も厳しく、金もなかったので、民家の四畳半一間を借りて住んだ。それもトタン屋根の庇を伸ばし、板で周りを囲うといった貧弱な家だった。だが、当時は一間でもいいから住めること自体がありがたかった。贅沢など言っていられなかったのである。
名護の町に住んでからは、漁業従事者で組を作り、船を所有した。我々は三十人で一つの組を作り、魚泉丸(七トン)を所有、名護漁港を拠点に恩納村沿岸辺りまで漁場として追い込み漁に励んだものだ。獲れたのはアカムロ、アジなどだった。漁から帰ってくるのは大体、午後三時ごろだった。
売りさばくのは女たちの仕事で、ヨシもその一員として獲れたばかりの魚を売りに出た。当時は履物もなかった。ヨシは魚の入ったバーキ(竹製のカゴ)を頭に載せ、裸足で売り歩いていた。名護の市場で売りさばけない時には、町から約八キロ離れた羽地村の振慶名まで足を運んだという。
長女の淳子が誕生してからは、ヨシは魚売りができなくなったので、名護の市場で野菜売りの手伝いをするようになった。
名護での生活にも慣れてきた。親戚の協力も得られるようになってきた。長女の淳子が生まれるまでには家も建てられるまでになっていた。ヨシの姉であるウシさんの夫、新城善一さんが山で切り取った材木を製材してくれた。我部祖河出身の人なら区長の許可を得て、集落の山から木を切り出すのは許されていたので、私も区長の許可をもらい、山から木を切り出した。これを善一さんがノコギリで製材してくれたので、その建材で家を建てることができたのである。当時、三間角と呼んでいたが、今日でいえば八畳二間プラス小さな台所付き、といったものだった。五○年(昭和二十五年)に入って、もっと金が稼げることはないか、と新たな仕事を探していたところ、伊豆味源徳さんの紹介で八重山を拠点にカイジン草(ナチョーラ)の収穫作業が金になるとの情報が耳に入った。戦前、台湾行きのきっかけをつくってくれた人でもあり、その言葉を信用して八重山に行くことになった。私は妻子を残し、一人船に乗り込んだ。
カイジン草は当時、学校で子供達の虫下しとして使われていた薬草である。深さ二、三メートルの浅瀬に生えていた。これを潜って手で刈り取り収穫するのである。 カイジン草の収穫作業に当たったのは漁民約三十人。我々は八重山を拠点に台湾の沖合にある中国領のプラタス諸島まで足を伸ばした。カイジン草は名護の原河の海でも採れたが、小さかった。せいぜい三、四センチぐらいのものだったが、プラタス諸島の海域ではその長さが二〇センチもあり、沖縄産と比べ、はるかに大きかったのである。
我々が乗ったのは五〇トンの船だった。カイジン草が繁殖しているポイントで我々は降ろされ、収穫作業に当たったが、周辺は寒流が流れ、海水は冷たかった。また潮水の流れも速く、作業は厳しかった。そのような状況からカイジン草は水がきれく、流れが速いところでないと繁殖しないことが分かった。
採れたカイジン草は陸上班の人たち約二十人が乾燥させ、箱に積み込んだ。これらのカイジン草は全部本土へ出荷された。一方、収穫した分量のうち半分は地元に与えるという約束だった。戦後、中国はアジアの大国として君臨しており、また外交上の問題などもあって、そのような対応をせざるを得なかったようだ。
この仕事を半年間やって帰ってきたが、伊豆見さんからは一円ももらえなかった。「約束が違う」と言っても埒があかなかった。この半年の出稼ぎは一体なんだったのだろう。ヨシはあきれ返っていた。「なんでウミンチュの妻になったのかね」と、愚痴をこぼし、自分を責めたようだ。これは後になって本人から聞かされたことである。私も立つ瀬がなかった。
一方、私の帰郷後、ヨシは生活の糧を求めて名護の市場で衣類販売の商売を始めた。二年ぐらい続けたと思う。衣類の仕入れはヨシの仕事。この時、長女の淳子はまだ一歳そこそこで目を離すわけにはいかなかった。衣類販売を手伝ってくれていた女店員に淳子を預け、ヨシは那覇の平和通りにあった卸問屋へ出掛け、商品を仕入れていた。当時は公営バスが 運行していたので、ヨシはそのバスを利用し、名護と那覇を行ったり来たりしていたようだ。
海の仕事のない日々が続いた。私はじっとするわけにもいかず、ヨシがやっていた店のすぐ隣(二部屋)が空いていたので、そこを借り受け釣り具店を始めた。この経験を生かし、私は六年後の一九五六年(昭和三十一年)にも再び名護市城で釣り具店を始めることになるのだが・・・。当然のことながら、私は釣り竿やオモリ、釣り糸など販売したが、店はそう長くは続かなかった。半年で店をたたみ、また海の仕事へ戻ることになったのである。
与論交易で家計潤う
ピンチの後にチャンスあり。カイジン草では収入がなかったが、このころ、与論との航海で一儲けできるチャンスが到来した。同じ年の一九五〇年(昭和二十五年)ごろだっただろうか。当時、流通していた貨幣のB円で約十五万円を出して船を購入した。無論、手持ち資金はなかったので、銀行から全部借り入れして買った。定員十人乗り、一〇トンの船である。私は船の名を「七福丸」と命名した。その名は「七福神」の由来からきている。奄美諸島が本土へ返還されるまで沖縄と奄美との渡航は自由だった。北部地方では運天港ー与論が航路として定着しており、私も七福丸の船主として商売に乗り出したわけである。最初のころは航海士の免許を持っていなかったので、与論の人を船長として雇い、日銭を稼いだ。そのころだった。ウエマ産業株式会社で現在、専務取締役をしている岸本文旭の父、徳勇さん(明治四十五年七月七日生まれ)も乗組員として船に乗り込み、一緒に仕事をしたものである。
当時はまだ生活物資が不足しており、与論からは人の往来はもちろんのこと、牛、馬、豚、山羊、鶏などの家畜類を沖縄へ入れた。与論は戦災を免れていたので、これらの家畜類を安く仕入れることができた。このため運天港は黒山の人だかりでごった返し、これらの牛、豚類はあっという間に売れたものである。
一方、沖縄から与論への物資は塩、ソーメンなどの食品や日用雑貨、またガソリンを運んで利潤を得た。沖縄で仕入れる商品の代金は与論の商売人が私に持たしてくれたので、私は資金に不自由することなく仕入れることができた。この時期、経済的にもかなり潤ったが、「与論の人たちのおかげ」と、今でも思っている。ちなみに運賃は大人二百円で、大牛は五百円、子牛二百円、豚は百円だった。七福丸は与論航海が主だったが、たまには佐敷にある馬天港まで航海し、豚などを降ろすこともあった。
だいぶ稼がせてもらったが、与論との航海が商売のコツをつかむ貴重な体験となったことは事実である。ところで与論島のことについて少し触れておきたい。与論は奄美大島諸島の最南端に位置し、沖縄本島から二八キロ離れた所にある。サンゴ礁の島で、真っ白い砂浜と青い海が魅力的だ。周囲二四キロ、面積は二〇平方キロ余、車で二、三時間も走ると一周できる小さな島。そこに六〇〇〇人余の住民が住んでいる(二〇〇三年九月末現在、二二五九世帯、六〇二九人)。
与論島には沖縄の三山時代に活躍した北山王の三男・王舅が築城した与論城跡がある。築城は途中で中止となったが、一四〇五?一四一六年ごろのものと見られる。与論は戦後、沖縄と同様に米軍統治下にあったが、一九五三年(昭和二十八年)十二月、祖国復帰を果たした。復帰前までは沖縄との往来は自由だった。与論は沖縄と違って、戦災を免れており、食料資源としての牛、豚、山羊などの家畜類は生き残っていた。このため復帰前後に活躍し、一旗上げた人たちが家畜類の仲買人、いわゆるバクヨウと呼ばれる人たちだった。
そのうちの一人が本畑實さん(明治四十年生まれ)で、平成十五年八月現在、九十六歳と高齢ながら、なお健在である。本畑さんの息子、本畑敏雄さんは、当時の話をよく聞かされたといい。「七福丸は金の船だった。バクヨウの仕事で金を稼ぎ、たくさん土地を買った。父が長生きできたのも、その時の蓄えがあったればこそである。本当に感謝している」と語っている。
沖縄からはガソリンや建材、ソーメン、チューインガムなどが島に持ち込まれた。七福丸の乗組員の堀田直常さん(昭和六年生まれ)は当時の状況をこう述懐する。「戦果としてガソリンを入手したことがあった。ガソリンの仕入れ価格はドラム缶(二〇〇リットル入り)が日本円で千三百四十円だったものが、島では七千円で売れた。実に五倍の値段で裁けたのである。当時の村長の給料は四千円。これに対し、我々の給料は七千円?八千円だった」と。世替わりの時期はまさにビジネスチャンスの時だったのである。船を利用しての生活物資の売買は、それなりに苦労はあったものの、魅力的な仕事の一つだったといえるだろう。
大型台風と格闘

船主として肝を冷やした経験がある。これは五一年(昭和二十六年)の出来事である。台風の名は「マージ」だったか「ルーズ」だったかは忘れたが、風速四、五〇メートルの超大型台風で県内各地に甚大な被害をもたらした時のことである。その時の乗組員は船主の私、船長の川端豊英、機関長・田端豊英(昭和三年生まれ)、甲板長・堀田直常の四人。台風は満潮で重なり風はかなり強く吹いていた。我々は他の漁船との接触転覆を避け、当初は馬天港近くでアンカーを下ろし、雨風をしのいでいた。だが、風雨は止むことを知らず、容赦なく我々の船をたたきつけてきた。
エンジンを停止していたら船が持たないと判断した我々は台風が通過するまでエンジンをかけっ放しにすることにした。風の方向に向かって船を進める手段に打って出たのである。船は風向きに逆らうように進行しようとするが、風があまりにも強く、その進路をちょうど阻止するような形で作用し、一定の場所にとどまった。 だが一〇トンの船も大海にあっては木の葉のように右に左に大きく傾き出した。その度に高波がどっと押し寄せ、甲板を洗い、引いていく。我々は船を守ろうと必死だった。だが、風雨は一向にやまず、そのうちアンカーをつなぎ止めていた三本のロープのうち二本が切れてしまった。私は「しまった!」と叫んだ。その時だった。乗組員の中では一番若い甲板長の堀田さんが海に飛び込んだのだ。
堀田さんは当時の心境を「海に飛び込めるのは私以外にいないと判断。それで荒れる海に向かって飛び込んだ」と述懐している。私に指示されて飛び込んだのではない。堀田さんは手探りで切れたロープを見つけ、それを甲板に引き上げてくれた。ロープは無事、つなぎ止めることはできたものの、これ以上、現場にとどまることは危険だった。
次の手段として我々は船を砂浜に乗り上げ、被害を最小限に抑えることを考えた。錨を上げた。船は浜を目指し、進路を変え、浜を目指し進んだ。馬天港に近づくと、港内は波がかなり穏やかであることに気付いた。そこで急きょ、港内に船を係留することを決め、我々は馬天港へ入港した。これは幸いだった。船が港に入った時、波風はだいぶ落ち着いてきた。我々は港で停泊したが、皆ホッとした表情だった。機関長の田畑さんは「本当に助かったと思いましたよ。その晩、一息入れて一杯飲みました」と当時を振り返った。
いずれにせよ、我々はこの大型台風を皆の協力で無事、乗り切ることができたのだ。正直言って私は船と一緒に心中する覚悟だった。今でも大きな台風が沖縄を通過する度に、当時のことが鮮烈に思い出される日々である。
七福丸とは四年ぐらい付き合った。五〇年には朝鮮戦争が起こり、日本はアメリカ軍の補給基地となった。武器の修理、軍需品の輸送、生産などを日本企業が引き受け、日本は一気に好景気となった。これは「特需景気」と呼ばれ、日本の高度経済成長の引き金となった。広大な軍事基地を抱える沖縄でも建設業を中心に県経済が潤った。また、くず鉄などのスクラップ業がにわかに脚光を浴びるようになったのもこの時期である。伊江島の沖合には沖縄戦で沈んだ米海軍の軍艦があった。この軍艦のスクラップを集めるために私の船も駆り出された。伊江島では民宿に泊まり込みしながら船を操り、利益を上げたものだ。その後、七福丸は薬きょう取りをしていた本部町出身の人に売った。
一方、名護の沖合には撃沈された日本軍の駆逐艦があったが、その解体作業に私は参加した。サバニ(小船)にコンプレッサーを積み込み、ダイバーを四、五人雇って海底に眠る駆逐艦のスクラップを巻き上げ、販売した。この解体作業は半年ほど続き、かなり収益を上げたことを覚えている。
この間、丙種航海士の免状も取得した。本部町の渡久地港内にあった施設で二週間、研修を受け、取得したものである。私の顔写真付きのその免状は、今も大切に保管しているが、それによると、取得した年月日は五二年(昭和二十七年)十二月十八日、とある。有効期間は五二年十二月十八日から五七年十二月十七日までの五年。免状は琉球政府行政主席名で交付された。
スクラップブーム
朝鮮戦争の特需景気で日本経済が活気を取り戻したのは先に触れた通りである。特に沖縄は、鉄の需要が一気に高まったことで鉄くず回収、いわゆるスクラップ・ブームに火がついた。この鉄くずの輸出は、これまで輸出のトップを占めていた砂糖輸出を上回るほど勢いがあった。そこで私もかかわったスクラップ業の最盛期について、沖縄で初めて鉄鋼業を立ち上げた拓南製鐵株式会社の創立者、古波津清昇氏の出版物「起業の心得帖ーチャンスを生かせ」を参考にしながら、当時の状況をたどってみたいと思う。
沖縄の海域に眠る軍艦等の廃品および地上に散在する不発弾など鉄くずは、戦後間もないころは米軍にその所有権があり、外国企業や本土企業が入札に参加し、米国政府と契約して大きな利益を上げる仕組みとなっていた。地元企業が入札に参加できたのは一九五三年(昭和二十八年)である。入札の権限を米国政府が琉球政府に委譲したことによるものだが、地元企業はこれに勢いを得て同年、四〇〇〇トンの鉄くず回収の落札に成功した。落札したのは拓南製鐵の前身である拓南商事と正和産業、丸宮商会の三社だったという。当時、鉄のスクラップはトン当たり四〇ドルだったものが、一気に一・七倍強の七〇ドルへはね上がるありさまだった。漁師も魚を採っているより鉄くずの回収作業が金になると判断し、サバニ(小船)二隻一組で回収作業に当たった。我も船を操り、廃船の解体と鉄くず回収に血眼になったものである。
さて、スクラップ輸出ブームの三年間、沖縄の対外収支は黒字を計上した。金額は次の通りである(ドル計算)。
▼五五年(昭和三十年)一、〇一〇万ドル
▼五六年(同三十一年) 四七〇万ドル
▼五七年(同三十二年) 九一〇万ドル
沖縄の総輸出に占める鉄くずは、この期間に飛躍的に伸びた。特に五六年は総輸出額二、〇一六万ドルのうち一、一六九万ドル(五八%)を占めるという成長ぶりだった。これまで主要品目としてトップの座にあった砂糖の輸出割合(三二・七%)をしのぐ勢いだったのである。
しかし、このスクラップ・ブームは三年で終わった。やがて鉄くずの価格は暴落し、取引が引き合わぬ状況となっていった。その後は製鉄の原料として県内の鉄鋼業界が買い入れ先となり、消費されるようになった。スクラップブームが終わった後の五年間の対外収支は大幅な赤字を計上した。
先に触れた通り、スクラップ・ブームの時期に私もサバニを繰り出し、海底に沈んだ軍艦の解体、回収作業に参加し、一儲けしたものである。スクラップは回収すれば金になるという時代で「スクラップ成金」も誕生した。
ザトウクジラを捕獲
その日は穏やかな日だった。七福丸は名護湾に停泊していた。乗客と貨物を載せ、これから与論へ向け出港しようとしていた。そんな矢先だった。漁船の廣泉丸から「鯨が名護湾に近寄っているので、応援してくれ」との連絡が入った。大きい鯨となると、少なくても二隻で挟むようにして山入端方面へ追い込み、クジラが自由に身動きできなくなったところで船上からモリで仕留めるのが通常のやり方だった。あいにく廣泉丸の僚船はドッグ入りしており、港には他の漁船はなかった。そんな折、湾内に貨客船の七福丸が停泊しているのを見て「これ幸い」と声が掛かったのである。
名護湾は明治の中期ごろからヒートゥ(ピトゥ)狩りといって、鯨の仲間であるコビレゴンドウ、オキゴンドウ、バンドウイルカなどの追い込み漁ができる湾として有名だった。名護の人たちの血がわき、肉躍るヒートゥ狩りは勇壮そのものであり、男も女も、農業をしている人達さえ、手を休め、浜に繰り出し、集団で回遊してきた鯨の捕獲に熱狂したものだ。鯨やイルカは、今でこそ捕獲が規制されているものの、当時は住民の唯一のタンパク源として重宝がられたものである。ヒートゥ狩りは延々と数時間にわたって行われた。鯨はモリで突き、捕獲する。このため湾内は鯨の血で真っ赤に染まった。
廣泉丸からの連絡で私の血が騒いだ。せっかくの連絡である。むげに断るわけにもいかない。早速、乗客と貨物を降ろし、漁師を乗せ、現場の沖へ向かった。
時に一九五一年(昭和二十六年)五月五日の出来事である。私は船主として参加、指揮船の廣泉丸の指示に従いながら、鯨を浜の方へと追い込んだ。鯨は大型のザトウクジラだった。体長は約一三メートル、重量にして六〇トンはあっただろうか。ヒートゥと呼ばれる小型の鯨とは大きさが全く違う。船の転覆も十分に予想された。クジラ漁は慎重に追い込みを図らないと、逆にこちらがやられかねない雰囲気だった。そのような緊張感の中で漁は行われたのである。
幸いというべきか、このザトウクジラは子と一緒だった。湾の入り口で大きく暴れることなく、浅瀬の浜へ追い込むことができたのはラッキーだった。廣泉丸の指示で捕獲開始の合図が出た。二艘に乗った漁師が一斉にモリを打ち込む。もちろん、船首にクジラ砲が設置されているわけでもない。モリは漁師が力いっぱい投げ込むのである。浜に追い込まれたクジラは自由があまり利かない。そこへモリの雨である。大きなクジラもついに力尽き、捕獲された。当時は世界的に見てクジラの数も多く、沖縄県民の食糧資源として一般家庭の食卓に上った。この名護のクジラ漁は季節的なものとはいえ、漁師らの格好の収入源となった。
私もそのおこぼれをいただいた。大物クジラの捕獲だったので、それなりの臨時収入が入り、懐が潤ったことを覚えている。家内のヨシも浜辺に繰り出し、陸揚げされたクジラの解体を手伝いながら、黒山の人だかりとなったお客さんに五斤(三キロ)、十斤(六キロ)と切って売った。クジラの肉はおいしく、肉は飛ぶように売れた。しかし、六〇トン余もあるザトウクジラである。さすがに一日では裁けずに、完全に処分する。
までに三日はかかったと思う。このザトウクジラの捕獲を契機に漁師たちの捕鯨への士気が高まり、また町民のヒートゥ狩りへの関心も一段と強くなったといわれる。
名護のヒートゥー狩り
さて、ここで春から初夏にかけて名護の風物詩となっていた、今はなき「ヒートゥ狩り」について、もう少し詳しく紹介しておきたい。
クジラ類は動物分類上はクジラ目といい、ヒゲ(髭)クジラ亜目とハ(歯)クジラ亜目に二分される。ヒゲクジラは口内に歯を持たず、クジラ髭を使ってオキアミなどの小動物を濾過して食べるが、代表的なクジラにはシロナガスクジラ、ザトウクジラなどがおり、一般的に大型だ。
これに対し、ハクジラは口内に歯が生えているクジラ類をいい、主に魚類やイカ類を食べる。ヒゲクジラに比べて小型で、体長もせいぜい四、五メートル以下のものが多い。名護でピトゥ(沖縄では一般的にヒートゥ)と呼ばれるクジラはコビレゴンドウをいう。だが、広い意味ではこのコビレゴンドウのほかに、オキゴンドウ、カズハゴンドウ、バンドウイルカ、マダライルカなども含まれる。
名護の漁師たちは、これらのクジラに対して昔から特別な意識を持っていたといわれる。特別な意味を込めてクジラのことを「テンシンガナシ」、またピトゥのことを「ピトゥガナシ」と「ガナシ」(神霊に対する敬称)を付けていたことからうなずけることだ。
ヒートゥは群れをなして回遊し、名護湾には主に三?六月の季節に接近する。名護湾の沿岸住民は海の沖合から来る生物や漂着物をユリムヌ(寄り物)として歓迎していた。ユリムヌにはヒートゥをはじめ、スク(アイゴの稚魚)、ガチュン(メアジ)などがあった。名護のヒートゥ狩りの起源は不明だが、「沖縄群島水産誌」(明治二十二年刊)には、明治二十年名護湾にヒートゥが来遊し、八十頭捕獲したと記されている。このころの追い込み漁は、来遊してきたヒートゥの群れに対し、船の上から石を投げて威嚇し、浜の方に追い込んでモリを投げて仕留めた。このような漁法は戦後、名護湾が埋め立てられるまで続いた。
ヒートゥの群れの規模は年によってまちまちだ。十数頭の年もあれば、二百頭近くの大群の年もある。
これまでの中では一九四一年(昭和十六年)四月一日の三百頭が最大規模だ。
名護名物のヒートゥ狩りは、漁師をはじめ名護沿岸の住民にとって大事な行事である。ヒートゥが来遊する時期になると、住民の血が騒ぐらしい。「ピトゥ、どーい」(ピトゥだぞ!)との触れ込みがあると、野良仕事に出掛けていた人たちも急ぎ家に戻り、軒下などに保管していたモリを片手に海岸に掛けつけ、ヒートゥ狩りに参加した。これは戦前の話だが、学校の卒業式の日に、ヒートゥが来遊した。「ヒートゥ、どーい」の触れ込みが式場に伝わった。一瞬、皆の顔色が変わった。先生も生徒も我慢できずに皆、浜に飛び出してしまい、式場には総代役のディキヤー(優等生)だけが取り残されたーというエピソードもある(昭和三年生まれの名護市港区の男性の話)。

釣り具店経営
上間金物店を経営する前に、名護市城で釣り具店を一年ほどやったことがある。金物店を始めたのが一九五七年(昭和三十二年)だから釣り具店はその前年の五六年(同三十一年)だったと思う。
釣り具店だから、釣り竿や釣り針、浮き、オモリなどを販売するのは当然だが、私の場合、オモリは港区の自宅で作り、城通りの店で販売した。どのようにしてオモリを作ったのか。まず原料の鉛だが、これは海底に沈んだ軍艦や米軍の払い下げ部品の中から鉛の部品を取り出し、これを鍋で溶かし、オモリを型取った鋳型に流し込み、固めて作ったのである。船は米軍が使用したケーブルの中に多く含まれていた。
鋳型はアルミと真ちゅう(黄銅)製の二種類。その鋳型はもちろん、手作りだった。名護鉄工所に働いていた奄美大島出身の方に作ってもらった。一般家庭のコンロで熱し、溶けた鉛を鋳型に流し込んで作るー原始的な作り方だったが、それでも結構作ることができた。このオモリ製造は自分一人でできるものではない。小さな狭い家で家内のヨシと一緒に苦労しながら作ったことを覚えている。
オモリは主に八号、三〇号、四〇号の三種類を作っていた。手作りだが、毎日コツコツと作っていくと、かなりの量になる。そうなると、自分たちの店だけでは裁ききれないので、那覇の壷川にあった釣り具店に卸すこともあった。私の記憶では四〇斤(二四キロ)のオモリを二人で担いで運んだことがある。那覇へ持ち運ぶ時には路線バスを利用した。那覇のバス停で降りた後は、その釣り具店まで歩いて持っていったものである。
釣り具店は一年ぐらいやったが、このオモリの製造、販売ではかなり収益を上げた。一方、釣り具店のことで思い出されるのは、学校の夏休みの時には子供たちに朝早くから起こされ、閉口したことである。名護の海岸は釣り場が多い。近くの海でガーラ(ひらあじ)がよく釣れたので、釣りをする子供たちが多かった。
夜も遅くまで働いていたので、朝早くから起こされるのは正直言ってきつかった。しかし、子供たちにとっては、何の関係もないことである。屈託のない子供たちのはしゃぎ声を聞けば、疲れきった体に鞭打ってでも対応して上げなければならない。この気持ちはヨシも同じだったと思う。今振り返ると、きつかったが、楽しい良き時代だったと思う。
上間金物店の立ち上げ
与論との交易やクジラ漁でかなり収益を上げた。私はその資金を基に今度は陸上で商売を始めることにした。当時、沖縄は日本から切り離され、米軍の統治下にあった。沖縄の人たちで組織する行政府として、琉球政府もできていたが、沖縄統治の最高権力者は米軍であり、米民政府だった。布令、布告の名の下に沖縄県民の人権は大幅に抑制されていた。
既に商売のコツを学んでいた私は、米軍の施政権下で金物店を始めることにした。一九五七年(昭和三十二年)春だったと思う。名護町の城通りに嶺井時計店があったが、ちょうど売りに出されていたので渡りに船とばかりに買うことにした。住宅兼店舗として改装し、金物店を始めた、店の名は私の性を取って「上間金物店」と命名した。現在ある上間鋼材株式会社、ウエマ産業株式会社の前身である。そのころ、二女の明美(昭和二十八年五月七日生まれ)は四歳となり、また三女の弘美(昭和三十一年十月五日生まれ)も既に生まれており、五人家族となっていた。私は三十三歳とまさに働き盛りだった。
金物店の商売を始めるに当たって、私には何か知らないが自信らしきものがあった。それは台湾での生活経験から機械への関心が強く、それなりに勉強してきたという自負心があったからである。「いい物は売れる」という信念みたいなものを持っていた。
当時、城通りには金物店が五軒あった。私の金物店ではボルトやワイヤー、ペンチ、金づちなどの工具を売っていた。米軍の施政権下では本土(日本)との取引も十分にできなかったので、店では米軍の払い下げ用品を売っていた。米軍でいったん使われたボルトなどは、水ペーパーやワイヤーブラシできれいに磨き上げ、販売した。磨き作業は家内のヨシと一緒にやることもあった。
沖縄には汽車や電車というものがなく、車が陸上の唯一の輸送機関だった。そこで私は米軍の払い下げトラックを購入した。
今でいう中古車だったが、そのままでは何の役にも立たないので、私はそのトラックを改造してクレーン車に作り変えた。
クレーン車の運転には免許が必要である。免許資格は那覇で取得しなければなかった。私は那覇で泊り込みしながら、講習を受けて免許を取得した。
クレーン車は重い物を持ち上げ、運ぶことができる。当時、クレーン車を持っている会社はまだ少なかった。名護町内では所有しているのは私ぐらいのものだった。そういう意味ではクレーン車を使う仕事は独占状態だったのである。
私の改造クレーン車は威力を十分に発揮した。琉球セメントやオリオンビールなどの工場建設では業務を一手に請け負った。
時には運天港に停泊している船の荷主の八重山開発から依頼があり、パルプ材に使われる木材を運搬する仕事もした。国頭などで取れたシイの木の原木を運んだが、源木は重さが一?一・五トンもあり、とても人間の手で運び出すわけにはいかなかった。
このため私に声が掛かり、その度に私は港に出向き、運搬作業を手伝ったのである。
運天港での作業は船の出発時間との関係もあって二十四時間体制で行われた。もちろん、私だけでパルプ材の運搬作業をやるわけにもいかず、助手作業員が必要だった。このため桑江良彦君(上間鋼材株式会社の現常務取締役)を補助作業員として使ったことを覚えている。
当時、彼はまだ十六、十七歳で県立名護高校の定時制に通っていた。夜の学校の授業が終わると、現場に掛けつけてくれた。クレーン車の操作は不慣れだったが、私の仕事を側面から手伝ってくれた。
桑江君は「会社から出してもらった大きな弁当の味が今でも忘れられない」と、思い出を語っている。
琉球セメント株式会社の設立は一九五九年(昭和三十四年)九月二十八日。旧屋部村(現名護市安和)に工場が落成したのが五年後の六四年(同三十九年)十二月十日である。火入れ式では創業者の宮城仁四郎社長の初子夫人が点火スイッチを押し、沖縄で初めてセメント事業がスタートした。
その工場建設に上間金物店のクレーンがうなりをあげ、忙しく立ち働いたのである。重い資材を持ち上げ、運んだりするなど、クレーンはフル操業した。このクレーンによる運搬作業は請け負い業務とはいえ、賃金は時間で決まっていた。当時はオペレーター込みで一時間三千五百円、ドルに換算して十ドルが相場だった。一般の労務の賃金に比べると、破格の賃金だった。琉球セメントの工場建設は名護鉄工所が請け負い、運搬作業で私が下請けするといったものだった。琉球セメントの工場建設にあたっては、特殊な技術が要求されることからドイツ人技師が派遣されていた。
名護市東江にあるオリオンビール株式会社。一九五七年(同三十二年)五月十八日に設立された沖縄唯一のビール製造会社だ。創業者、具志堅宗精氏が「戦後の沖縄の経済を復興するには第二次産業を興さなければならない」との強い意志に基づき、創設されたもので、そのビール工場建設にもかかわった。工場建設は同年八月に始まり、翌年の五八年(同三十三年)十一月に完成した。名護鉄工所が請け負い、その下で私が働くというパターンだった。人がやっていないクレーン作業だったので、仕事はほぼ専属的なものだった。競業する会社がなかった分だけ、仕事は安定し、それなりに収益を上げた。
一方、米軍の払い下げ品を求めて私は宜野湾市大謝名や浦添市の牧港方面へよく出掛けたものである。米軍の払い下げ品を卸す業者には私が所有する車を有料で貸しながら、金物店で売れそうな部品を買い集めた。ある時は部品の調達で三ヵ月間も大謝名に泊り込むこともあった。家内のヨシは心配したが、私は必死だった。店と子供はヨシに任せきりにして部品調達に奔走した。家内は店を切り盛りし、私は商品(金物の部品)を仕入れることに全力を挙げた。
その当時を振り返り、ヨシは「お客さんが仕事を教えてくれた。お客さんに感謝する毎日だった」と述懐している。この二人三脚の仕事が続けられたからこそ、人より多く利益を上げることができたのであり、それが会社を興す原動力となったのである。「人がやらないことをやる」?それが私の経営理念となった。
アメリカ製のボルトなどの部品は耐久性に優れ、お客さんから人気があった。特にヤンバルでラージ(四分の三トン車)や二・五トンのベーカ車など使って木材の切り出し、運搬作業をしている業者からよく注文があった。起伏の激しい国頭村奥や辺土名など山奥では車をかなり酷使したので、ボルトの消耗が激しかった。このためボルトの買い替えも多く、頑丈なアメリカ製のボルトがよく売れたというわけである。日本製などは見向きもされず、まさに「アメリカ製さま、さま」だった。
城通りにあった上間金物店は順調に売り上げを伸ばしていった。クレーン車による請け負い業、ボルトなど金物の売れ行きは好調で、経済的にもゆとりが出てきた。この時期に長女、二女、三女に続いて四女の京子(昭和三十四年九月十日生まれ)、五女のみちる(同三十七年四月二十二日生まれ)、長男の雅之(同三十九年九月十八日生まれ)も相次いで誕生した。六番目に生まれた雅之は初の男の子で、私の後を継ぐ嫡子として喜びもひとしおだった。この結果、我が家は八人の大家族となった。
仕事も大変忙しかったが、子供たちの澄んだひとみ、純真無垢な笑顔、茶目っ気な素振りに元気付けられたものである。子宝に恵まれ、家庭的には申し分はなかった。子供たちの成長とともに「家族のために」との思いも強くなり、仕事に一層熱が入った。
合資・有限会社設立
一九七二年(昭和四十七年)五月十五日、沖縄は日本復帰を果たし、新生沖縄県としてスタートした。アメリカ世から大和世への世替わりである。復帰の年の翌年(七三年)、業務を拡大するため名護市東江に東江ヤードを併設した。重機類など設置し、本格的にレッカー業務およびレッカーのリース事業を始めた。レッカーはアメリカ製のラージ(四分の三トン)、また二・五トンと五トンのレッカー二台も配置した。このレッカー事業と並行してアメリカ製のボルトや工具など金物部品を売る金物販売事業は続行した。
七二年(同四十七年)十一月、名護湾の埋め立て工事が始まった。この時には国産(タダノ、カトウ)のトラックレーン(二〇トン車)を保有するまでになっており、埋め立て工事にも参入した。我々が引き受けたのは護岸工事で護岸に大きな石を積み上げる、いわゆる「石積み工事」だった。また名護の七曲りを拡張する国道五八号の道路工事にも積極的に参加、クレーンやレッカーによる工事部門の拡大を図った。
その際の笑い話もある。我々のクレーン車などには「上間金物店」と店の名前が書かれており、本土のゼネコン(大手の総合建設会社)からは「金物店がなぜ、こんな工事現場に?」と不審がられる一幕もあった。社員も苦笑いしながら対応したようだ。
一九七五年(昭和五〇年)七月、本島北部の本部町で鳴り物入りで開催された沖縄国際海洋博覧会を挟んで七六年(同五一年)には「合資会社上間鋼材」を設立した。東江に新社屋を建設し、鋼材の加工業と販売事業に進出した。業務の効率化を期すにはコンピューター導入は欠かせない。しかし、コンピューターは当時、かなり高価だったが、業務の迅速化、省力化のために電算化する必要があったので、七九年(同五十四年)、
他社に先駆けてコンピューター導入に踏み切った。
コンピューター導入から九年後の一九八八年(昭和六十三年)五月、城通りから北へ約二・五キロ離れた所にある名護市大北に敷地を求め、金物店を新築、大北店としてオープンした。一方、同年八月には同市伊佐川にトタン成形工場を建設し、トタンの成形、販売事業にも着手した。この八八年は店舗の新築とともに、新規分野の開拓に乗り出した年だった。
幸い、資金的にも余裕があったので、さらに売り上げを伸ばそうと、業務拡張に乗り出したのである。話は前後するが、海洋博覧会の話に戻ろう。海洋博は沖縄の本土復帰を記念して七五年七月二日から六カ月間にわたり、伊江島を望む本部町で開催された。四面、海に囲まれた沖縄。その海洋資源を生かした沖縄の未来の姿を展望して、メーンテーマも「海ーその望ましい未来」だった。政府が投入した事業費は実に総額二三七一億円だった。沖縄経済の起爆剤にとの触れ込みで入場者は述べ四五〇万人が見込まれたが、実際に入場したのは予想より百万人も少ない延べ三五〇万人だった。短期間の博覧会だったが、終わってみると、地元企業の倒産が相次ぐなど、「海洋博後遺症」を残した。
上間金物店は海洋博工事ではそれなりに潤った。直接、工事を請け負うことはなかったが、期間中、工事に伴う部品、例えばチェーンブロック、レバーブロック、タンパックル、ワイヤー、ボルトなどがよく売れたのである。この時には沖縄が本土復帰して二、三年経過していたので、部品はすべて本土メーカーの物を仕入れていた。仕入れ先は確か、大阪の近藤鉄工だったと思う。
七六年(昭和五十一年)の閉幕後に解体工事が始まったので、店のクレーン車を持ち出し、解体作業に参画した。また使用済みのH鋼などの資材を払い下げてもらい、これを店で販売して収益を上げた。
昭和天皇が逝去され、「平成」の時代に入った。ここで平成の時代に入ってからの歩みを簡単に振り返ってみたい。九〇年(平成二年)には名護市伊佐川にレッカー事業部門を移した。九二年(同四年)十二月、同市城で三十五年も営業を続けてきた上間金物店を閉めた。これは同市大北で業務を一元管理するための措置だった。
九三年(同五年)一月、金物販売事業部門を法人化することになり、「有限会社ユーテック」を設立した。またレッカーリース部門を杭打部門を法人化し、「有限会社ウエマ産業」を設立した。一方、この一月に名護市伊佐川にあった有限会社ウエマ産業を名護市大北に移転した。九六年(同八年)一月、名護市東江にあった合資会社上間鋼材を大北へ移転、新築した。この結果、上間鋼材をはじめ、有限会社ユーテック、有限会社ウエマ産業の三つのグループ企業を一ヵ所に集めることができた。これで各企業が連携して業務を遂行できる体制が構築された。
株式会社へ移行
平成に入り、経済は低迷している。「平成不況」と呼ばれ、金融機関や保険会社、ゼネコン(総合建設業者)などの倒産が相次ぎ、深刻な経済状況を作り出している。この経済状況を冷厳に認識し、会社組織の改編に踏み切った。
二〇〇二年(平成十四年)十一月一日、合資会社上間鋼材と有限会社ユーテックを合併し、上間鋼材株式会社を設立した。また同日、有限会社ウエマ産業をウエマ産業株式会社に格上げし、対外的な信用を高めることにした。
株式会社設立に先立つ九年前の九三年(平成五年)一月二十七日、取締役社長のポストを私の長男、雅之に譲った。私は代表権を持った取締役会長に退き、大所高所から補佐することにした。会社合併に当たって社長の雅之は「金物販売事業と鋼材部門は、一体化することにより経費が抑制できるというメリットがあった。鋼材分野も不況を反映し、年々、競争が激化してきているのが現状。統合化することで体力を強化することが必要」と話している。私もその考えには同感だ。
新しい酒は新しい皮袋に盛れー。時代は移り、IT時代を迎えた。コンピューター技術などは昔は知らなくても仕事はできた。しかし、これからは違う。IT技術なくしては生きられない世の中になってきたのだ。新しい仕事を託するには若い人しかいない。社長のバトンタッチもそのような時代背景がある。雅之は二〇〇三年(平成十五年)五月、沖縄県商工会青年部連合会の会長に就任した。一期二カ年だが、青年の力で沖縄の地域経済が少しでも活性化できれば、と期待している。
上間鋼材㈱の将来展望について、雅之は「単なる物だけの販売では通用しない時代を迎えた。物をベースにしながらも、これにどう付加価値をつけ、販売していくかが大事だ。そういう意味で企画提案型の事業展開を目指していきたい。できれば、上間鋼材の加工技術を生かして自主ブランド製品を開発できればと思っている」と抱負を述べている。会長としても頼もしい限りである。
社員は現在、三十三人。大規模の事業所とはいえないが、我々のスローガンは「「やんばると共に前進する企業」と、夢は大きい。グループの経営理念は「社業を通し、地域社会の事業に積極的に参加し、その発展に貢献する」「社員の目標と家族の夢と幸せの実現をアシストする」「自己の技術と知識を最大限に生かし、お客様の成功と自己の成長を最大の喜びとする」の三つだ。国の施策の北部振興策が実施されて四年。二〇〇四年(平成十六年)は五年目に入ったが、我々はこの千戴一隅のチャンスを最大限に生かし、地域(やんばる)と共に、大きく成長し、発展していきたい、と念じている。
二〇〇四年が明けた。市場は新しい価値観の形成と信頼性が強く求められるようになってきた。上間鋼材㈱やウエマ産業㈱、(有)ユーテックのグループ企業も同様なことがいえる。そこで雅之社長は陣頭指揮を取り、対外的な信用力を高めるための措置を講じた。
-
上間鋼材株式会社
- 代表取締役会長
- 上間義夫
- 代表取締役
- 上間雅之
- 専務取締役
- 桑江良彦
- 取締役
- 上間ヨシ
- 取締役
- 上間優子
-
ウエマ産業株式会社
- 代表取締役会長
- 上間義夫
- 代表取締役
- 上間雅之
- 専務取締役
- 岸本文旭
- 取締役
- 上間ヨシ
- 取締役
- 上間優子
(二〇〇四年七月現在)
我部祖河そば
琉球料理の一つに沖縄そばがある。沖縄のそばは本土のそばと違って、麺にはメリケン粉(小麦粉)を使う。また、それにダシ汁(スープ)は鰹節のほか、豚骨など使い、ゆっくり煮込むので、独特の風味をかもし出しているのが特徴だ。沖縄県民はそばが大好物である。麺料理で、かつ消化も早いことから、食事時間を気にしないで、気軽に食している。沖縄の至る所にそば屋ののれんが出されているのもそのせいだ。
沖縄そばは、具の中身によって「ソーキそば」「三枚肉そば」「肉そば」「野菜そば」などのメニューに分かれる。しかし、定番は何といっても「ソーキそば」だろう。このソーキそばの生みの親が私の従兄弟に当たる金城源治さん(昭和四年一月十日生まれ)が経営する我部祖河食堂だ。源治さんは、私の母・カマダの弟、金城善照さんの長男である。
我部祖河の偉人
沖縄の自由民権運動家・謝花昇、移民の父の当山久三は郷土の歴史教科書に出てくる偉人である。偉人とは何か。その基準は難しいが、一生をかけて「人のため、世のために尽くす人たちである」と捉えたい。その意味では歴史に埋没した感のある名護市我部祖河出身の上間幸助を偉人として推挙し、この功績を永くたたえるべきだと考える。宿縁があって上間幸助は上間家の門中の大先輩に当たる。屋号は仲ノ屋で、一八七〇年(明治三年)一月十七日生まれの人物である。
私が偉人として推挙するのは「国政に衆議院を送り出す参政権が沖縄県にまだ与えられていなかった明治時代中期に職をなげうって謝花昇や当山久三らと共に上京、自由民権運動に参画したこと。また当時の奈良原繁県知事らの執拗な弾圧によって運動が挫折した後は、当山久三の移民事業に同調し、海外移民の初期に我部祖河からは初めてアメリカ大陸(米カリフォルニア州ロサンゼルス=明治三十五年十一月)へ渡り、自ら移民の先駆けとなって本島北部の人たちに大きな影響を与えた」などの理由からである。不幸にも志半ばにして享年三十七歳の若さで逝去したが、彼が残した功績はきちんと評価されるべきであろう。
幸助は旧羽地村の我部祖河に生まれ、一八九〇年(明治二十三年)に沖縄師範学校を卒業した。二つ年上の金武村出身の当山久三とは同期生の仲で、当山も同じ年に師範学校を卒業している。二人は対照的だ。幸助が金武小学校の訓導(教員)になったのに対し、当山は逆に幸助の出身地、羽地尋常小学校へ訓導として赴任している。幸助に関する資料は乏しく、情報も一部交錯しているが、分かる範囲内で紹介すると、幸助の家計は代々、農業を営んでいたが、暮らし向きは裕福だったという。体は小さいが、情熱的で議論好きだった。一度議論すると、相手を屈服させずにはおかないほど論理的思考を身につけていたようだ。
彼が謝花昇の運動に共鳴を覚えたのは、謝花が当時の最高権力者、奈良原知事(鹿児島県出身)と堂々と渡り合い、民権運動の必要性を訴えていたからだ。彼は謝花の主張に心を動かされ、ついに小学校の訓導を辞して、謝花の元へはせ参じ、共に行動した。「義人謝花昇伝」を刊行した作者の大里康永氏は、この幸助の行動について「官尊民卑の時代であり、官吏教員のごときはすこぶる有難がられていたのであるが、躊躇せずに職を捨てて民衆の隊伍に入ったことはすこぶる注目すべきことである」と述べている。
また大里氏は参政権運動で謝花昇が当時、内相を務めていた板垣退助らに会うため上京した際、沖縄の代表者として七氏を挙げているが、その中にも幸助はいる。大里氏の著書「自由への歩みーわが思い出の記」によると、請願運動の代表者として謝花昇を筆頭に、長田秀雄、具志保門、渡慶次一、喜納昌松、当山久三、上間幸助ら七人を列挙している。そして大里氏は幸助の活躍について、書く資料を持たないのは残念である、としながら「謝花、当山のごとく熱心に運動を続け、権勢にも恐れず、誘惑にもなびかず、大いに参政権のために努力したことは、県民の永く忘るべからざるところである」(「義人謝花昇伝」)と幸助の運動を高く評価している。
奈良原知事の弾圧はすさまじいものであった。上京中の謝花らが投宿する旅館に暴力団を差し向けて襲い、また、運動資金の財源であった機関紙「沖縄持論」の発行元、南陽社の経営を破壊するなど、運動を撲滅するために手段を選ばなかった。このため運動は挫折し、謝花は生活が困窮、職を求めて山口県へ赴く途中、神戸駅で発狂、その七年後、病死した。享年四十四年だった。
自由民権運動は挫折したが、その精神は確実に継承された。やがて沖縄でも本土同様に参政権が得られたのである。辛く厳しい道のりであったー。
自由民権運動に挫折した人のその後の人生はさまざまである。当山久三は海外への移民事業に奔走した。沖縄の移民の開始は一八九九年(明治三十二年)である。その年、ハワイへの移民で県人二十七人が沖縄を離れた。二回目は一九〇三年(明治三十六年)でハワイとアメリカ本国へ九十六人を送り出している。
幸助も移民事業に活路を見出すべく、一九〇二年(明治三十五年)十一月、学術研究を目的に米カリフォルニア州ロサンゼルスへ渡った。三十二歳の若さだった。幸助は失意の中にあって新天地を求めての渡米だったに違いない。彼のロサンゼルスでの生活ぶりはどうだったのか。「在米沖縄県人概史」によると、渡米した後輩を大事にし、よく面倒を見ていたという。また結婚せず独身だったようだ。移民から五年、幸助は子孫も残さずにこの世を去った。一九〇六年(同三十九年)九月二十七日のことである。享年三十七歳であった。
この死亡年月日は、「我部祖河誌」(平成十一年十二月発行)によるものだが、別の資料「在日沖縄県人慨史」によると、一九〇八年(明治四十一年)八月、心臓病で倒れ、ロサンゼルスのホテルで後輩らに見守られ、息を引きとったという。この場合だと、享年三十九歳となるが、真偽のほどは定かではない。異郷の地での死はどういうものだったのか、わが古里ー沖縄、そして我部祖河への思いは・・・。死出の旅路への悲しみは深い。
自由民権運動に参画した三人の生涯年齢は、謝花昇四十四歳、当山久三四十三歳、上間幸助三十七歳。あまりにも短い生涯だった。しかし、短い人生にあって「世のため、人のため」と願い、自分の信念をぶつけ、闘い、傷つきながらも、強く生き抜いたその生き方に学ぶ点は多いと思う。
我部祖河の豊年祭
米どころとして知られた我部祖河。戦前、我部祖河一帯は羽地田袋と呼ばれていたことからもうかがえよう。区の豊年祭は旧暦の八月八日に執り行われるが、その起源は一八八七年(明治二十年)といわれる。区の御獄で祈願したあと、組踊りや棒術など奉納したという。
我部祖河の豊年祭は一九四四年(昭和十九年)、沖縄戦で中断したが、戦後の四七年(同二十二年)に復活した。昭和三十年代に入り、豊年祭は活性化し、近隣町村から観客が訪れるほど有名となった。だが、毎年行われていた豊年祭も一九八六年(同六十一年)からは三年ごとに行われるようになり、今日に至っている。「我部祖河誌」によると、三年ごとの開催となった理由は、新生活運動や踊り手の都合によるものだという。
さて、二〇〇三年(平成十五年)九月六日、伝統の豊年祭が執り行われた。公民館前広場にはウエマ産業㈱のクレーン車が出動、大規模の天幕が張られ、ムードを盛り上げた。まず、十三年ぶりに復活したというスー巻き(潮巻き)棒が披露された。
中高校生以上の男子約五十人が声を掛け合いながら円陣を組み、全体で棒の舞いをしたあと、おのおの二人が広場中央に進み、勇壮な組手棒を披露。その度に参観者は盛大な拍手を送った。午後六時半から始まった豊年祭も夜のとばりに包まれるころから次第に熱を帯びてきた。
会場には区民や通りがかりの人たちも詰め掛け、参観者は千人に膨れ上がった。スー巻き棒のあと、舞台は公民館に移され、そこで催し物が次々と披露された。参観者は家で作ってきたご馳走をほおばりながら芸能を堪能。また出演者も日ごろ鍛えた練習の成果をここぞとばかりに遺憾なく発揮、参観者と一体となって豊年祭を盛り上げていたのが印象的だった。古里の豊年祭は実にいいものである。ここで出演者の労をたたえるため、当日行われた演目を紹介するとー。
- 「かぎやで風」
- 獅子舞
- 組踊「長者の大主」
- 「女花笠」
- 「上り口説」
- 大正琴
- 日舞「黒田節」
- 老人会「クェブゥ沖縄」
- 「浜千鳥」
- かせかけ
- 「花風」
- 「下り口説」
- 「谷茶前」
- 「汀間当ー」
- エイサー
- 日笠踊り
- 「カナヨー」
- 日舞「風雪流れ旅」
- 「鳩間節」
- 「繁昌節」
- 「前之浜」
- 日舞「桜の花の散る如く」
- 「松竹梅」
- 「万才」
いずれの演目も圧巻だった。我部祖河には芸達者の人たちが多いことに今さらながら驚かされた。老朽化が激しい公民館。この公民館での豊年祭は今回が最後となった。
城区と共に
現在の会社の礎を築いたのは、名護市城区にあった上間金物店である。その折々に触れたが、上間金物店を立ち上げたのが一九五七年(昭和三十二年)。営業拡大と同市大北への会社移転に伴い、城区の金物店を閉めたのが一九九二年(平成四年)十二月だったので、実に三十五年間、城区で仕事と生活を送ったことになるのである。まさに公私共に城区とのかかわりは深い。
今住んでいる住宅は、島の隣の同市東江だが、私の人生は城区を抜きには語れないので、ここで城区とのかかわりについて少し触れておきたい。行政区としての城区の名は、名護城に由来する。発祥は二百五十年前で、名護城に住んでいた人々が平地を求めて移り住んだという。戦前は東江、大兼久と一緒に「名護三力」と呼ばれるほど、大きな集落を形成していた。戦後は一九六六年(昭和四十一年、三九一世帯一九七六人)をピークに人口は減少の一途をたどっている。行政区の面積が小さく、住宅建設がままならないのが大きな理由だ。二〇〇三年(平成十五年)現在の人口は五八〇人(一七〇世帯)である。
城の主な行事の一つに旧暦の九月九日に行われる豊年祭がある。名護城にある御獄で祈願したあと、種々の芸能を奉納するが、私はこの豊年祭について、いろいろと協力してきたつもりだ。一九九六年(昭和六十一年)四月以来、長期にわたって区長をしている山入端信博さんは「家族みんなで応援、協力していただいた」と述べている。気恥ずかしい思いもあるが、区長のまじめなコメントとして素直に受けとめたい。また雅之も区の青年会長を務め、彼なりに区の発展に尽力した。このことは周辺の人々が認めるところである。 さて、区には劇作家の比嘉宇太郎氏がいる。戦前、新聞記者をして戦後、名護町長や立法院議員など務めた方で、豊年祭における組踊上演では多くの作品を書き上げ、区民を大いに歓喜させたことで有名である。作品に「許田の手水」「シガマ森」「ヒートゥドーイ」などがある。
私の家族がかかわった豊年祭の芸能には組踊「銘苅子」と「国頭サバクイ」がある。「銘苅子」は玉城朝薫が創作した組踊五番の一つで、羽衣伝説を舞台化したもの。その天女の役をしたのが二女の明美だった。親ばかと言われるかもしれないが、明美の演劇には感激を覚えたものである。三〇〇人ほどの区民も温かい声援を送ってくれ、うれしかった。
「国頭サバクイ」は、昔、国頭地方で伐採した材木を首里王府まで運ぶ際に歌われたといわれる労働歌・踊りである。サバクイは地方役人の職名。「国頭サバクイ」は、サバクイの指揮の基に多くの男女がきつい運搬作業に従事させられた史実に基づき、芸能化されたものだ。城の「国頭サバクイ」は名護の桜祭りの行事にも出演するほど有名である。私は「城国頭サバクイ保存会」が設立された際、副会長を務め、保存に努力したものである。「国頭サバクイ」が演じられたのは百年前ともいわれ、歴史は古い。名護市に残るこの芸能を我々の世代で終わらせてはいけないと思う。ヤンバルの人たちの苦悩の歴史を歌や踊りで伝えることは、教育の面からも意義があるのではなかろうか。
「国頭サバクイ」に関して、私は出演者の衣装を準備する「衣装担当」を任せられた。目に見えない裏方の仕事だったが、私なりに頑張ったつもりだ。私たちの地道な努力は認められ、一九九六年(平成八年)十一月、「地域文化の振興に寄与した」として沖縄県文化協会(池原貞夫会長)から保存会へ感謝状が贈られた。
区の公民館は地域の人たちにとって、唯一の交流の場である。公民館の備品の充実は大切だ。一九九四年(平成六年)、公民館の新築に伴い、合資会社上間鋼材は舞台幕を贈呈した。またガジュマルの大木も寄贈したが、これは台風の影響を受け、残念ながら幹は枯れてしまったが、今、傍らから新芽が伸びている。
十五年ぐらい前にはグランドゴルフ用具一式を贈ったが、これは現在も使われているという。山入端区長や大城章一さん(区老人会長)らは「老人会活動で有効に使わせてもらっている」と話している。
私は体調を崩す前までゲートボールを大いに楽しんだものである。当時、私も選手だったが、城の老人会は強かった。私が記憶するものでは一九八二年(昭和五十七年)十二月、名護市老人ゲートボール大会準優勝、八三年(同五十八年)十二月、同大会優勝、八四年(同五十九年)六月も優勝という輝かしい成績を収めている。その時の準優勝、優勝メダルは今も大切に保存している。
地域への貢献
事業を興して収益を上げたならば、その一部を社会へ還元するのは事業家の務めであろう。私は社会への恩返しの気持ちで地域への貢献をささやかながらやってきたつもりである。私は、自分ができる範囲内で何件か寄付させてもらったのだ。また金には代えられない地域活動もしてきた。これらの行為を私は鼻に掛ける気持ちはさらさらないが、後進のために、幾つかの感謝状を通して、その足跡の一端をとどめておきたいと思う。
私の子供は六人いるが、子供たちは名護市東江小学校出身である。東江小学校創立八十五周年を迎えた際、記念事業資金として寄付したが、一九六八年(昭和四十三年)五月、仲宗根善行校長、山端浩記念事業期成会長は連名で感謝状を授与した。私は同市城大通り会が標榜する「明るく美しく住みよい町づくり」を目指して、通り会の副会長を二期務めてきた。この功績がたたえられ、七一年(昭和四十八年)十一月、城大通り会(利根一夫会長)から感謝状をいただいた。また、このころ城大通りにはまだ街路灯が設置されていなかった。夜は暗く、区民は長い間、街路灯の整備を望んでいたが、幸い町当局(当時)の補助金と区民の芳志で街路灯が設備された。私も通り会の一員として、物心両面にわたり協力したため、七一年(昭和四十六年)十二月、城大通り街燈設置委員会(新田宗俊会長)から感謝状を授与された。
東江小学校が児童生徒の情操教育の一環として、自然を大切にする心をはぐくもうと洋式の庭園造りを企画した。私は庭造りに必要な樹木や石岩を運搬するために、わが社のレッカーを出動させるなど、全面的に協力した。庭園は学校側とPTAの協力で完成した。沖縄が本土復帰した時期の一九七二年(昭和四十七年)五月、東江小学校(宮城盛雄校長)、同小学校PTA(比嘉栄明会長)の連名で感謝状をいただいた。感謝状には「この芝生園(庭園)のもつ教育的意義は深く、かつ大なるものがあります」と記述されている。
私も当時、四十八歳と働き盛りで、子供たちのためにと頑張ったものである。そのころ、同小学校に在学していた私の子供は四女の京子、五女のみちる、長男の雅之三人だった。
東江小学校の体育館建設に合わせて、内部の設備のを充実させる必要があった。私もその趣旨に賛同し、学校に寄付した。七五年(昭和五十年)六月、東江小学校(中村正己校長)、体育館建設期成会(大城森男会長)は連名で感謝状を授与した。
城大通り会の副会長を二期務めてから十年後に会長職の大役をおおせつかった。私は十代目の会長だった。私なりに全力を尽くしたことに対し、「会員相互の親睦と福利増進を図り、通り会の進展に貢献した」として、八四年(昭和五十九年)六月、城大通り会(渡具知武朝会長)から感謝状をいただいた。
戦前、北部地方の川には魚やエビなどが棲んでおり、子供たちは水遊びしながら釣りをして楽しんだ。
その幸地川を昔のような清流にしよう、と取り組んでいる自然保護団体があり、私は運動に賛同する立場から同団体を支援した。九二年(平成四年)四月、幸地川を蘇生させる会(富名腰春子会長)から感謝状を授与された。
地域への貢献事業は個人レベルから会社レベルのものまで、いろいろある。名護市城の区民会館建設に当たっては、合資会社上間鋼材(当時)として建設費の一部に、と寸法を寄せた。九四年(平成六年)十一月、城の区民会館建設期成会(山入端信博会長)から感謝状が贈られた。
これは一身上のことだが、私は日本クレーン協会沖縄県支部の役員を長い間、務めたことがある。このため支部設立二十五周年を記念し、同県支部(石川逢重支部長)は九九年(平成十一年)四月、記念品と感謝状を授与した。
二〇〇〇年(平成十二年)七月、沖縄で主要国首脳会議(沖縄サミット)が開催された。厳戒な警備体制が敷かれ、有限会社ユーテックは社を挙げて警護活動に協力した。サミット閉幕後の同年八月、名護警察署(比嘉正輝署長)と名護地区地域安全協力会(仲泊弘次会長)は連名でユーテックに感謝状を授与した。
また、これは長男・雅之のことだが、雅之は名護市商工会青年部の部長時代、沖縄サミットの成功に向け、持ち前の企画力と行動力をもってサミットに協力した。このため、二〇〇一年(平成十三年)五月、部長退任に際し、同市商工会(荻堂盛秀会長)から感謝状を授与されたことも付記しておきたい。
私は我部祖河出身である。集落の豊年祭は私の楽しみの一つだ。私は我部祖河に生まれたことを誇りに思っているし、これからも生まれ故郷を大切にしていきたいと思う。かつて我部祖河には恩返しとして舞台幕を公民館へ寄贈したことがあるが、今後も側面から応援し、協力をしていくつもりだ。最後に「自分史」を締めくくるに当たり、改めてわが故郷・我部祖河に発展あれ、と祈念するものである。